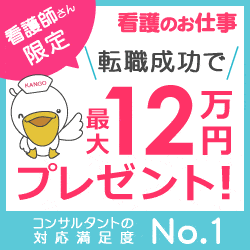手術室看護師の教育プログラムってどんな内容?
手術室勤務ならではの勉強が必要?
手術室の看護師の役割は
①「直接介助(器械出し)」
執刀医らの脇にいて、メスなどの手術器具を手渡しする
②「間接介助(外回り)」
足りなくなった薬品類の補充、急に必要になった機械・器具類の用意、室温・湿度などの調整など、直接介助以外のすべてをやる
…のふたつに分かれます。
ひとつの手術の中で、一人の看護師がこの両方を兼ねることは、基本ありません。
このどちらを担当しても、ほかの診療科で行う「看護師としての基本的なスキル・知識」とされるようなことは、全くやらないのです。注射・採血などはありません。ベッド上の患者さんの体位交換もなければ、食事・排便の介助もありません。
そのため、他の科から看護室に配属されたときは、新しく知識として覚えなければならないこと、スキルとして習熟しなければならないことばかりです。
「一人前になるまでに、器械出しは3年、外回りなら5年はかかる」といった声も聞かれます。
「直接介助」から学ぶ
一般的にはまずは「直接介助」からやることになります。というのは、「間接介助」は全体を見渡し、病院内のほかの部署との連絡・調整も任されるので、一層経験が重要になるからです。
教育プログラム
この直接介助を始めるにあたっての訓練方法は、病院によって様々です。
①ほかの診療科の看護師と共通の教育プログラムがあるだけ。後は実際の仕事をやりながら覚える
②数か月程度の手術室看護師専用の教育プログラムを用意している
③新人看護師は手術室には配属しない。外科病棟などで、2、3年、看護師としての基礎を積んだ後に、手術室に異動させる
などのパターンがあります。
いくつかの特徴、補足をあげてみると
・パッと見では、②がベストのように見えますが、それぞれ一長一短があります。
・「手術室看護師専用の教育プログラム」にしても、病院ごとに充実度に違いもあります。
・①~③のどれであっても多くのところで、プリセプター制度を採り入れています。つまり、新人ひとりずつに、教育係の先輩看護師が付きます。
・やはり大病院は力を入れている!
中には
「手術室教育委員会」「手術室新人支援体制」などいったチームを作り、教育係もそれぞれジャンルごとに手分けする。1~2年かけて、システマティックに手術室の新人教育を進める
といった病院もあります。
こういったように教育プログラム・教育体制が整っているのは、大きな病院に多いです。特に大学病院です。
・他科経験者も一から勉強が基本
また、③のように外科病棟などですでに看護師として一通りの経験をしてきている人も、手術室内では「一からやり直し」と考えたほうがいいでしょう。
それぐらいほかの診療科の看護師と仕事内容が異なるのです。
自分には向いていないと感じたら?
中には「希望していなかったのに手術室に配属された」「自分には向いていないみたい。すぐにでも異動・転職したい」といった人もいるでしょう。
そこでがんばるのがいいのか、すぐにでもよその診療科に移った方がいいのかは、難しい問題です。
いずれ移るにしても、新人がキャリアを手術室から始めることについては、プラスに考える人と、マイナスに考える人の両方がいます。
プラスに考える人
・緊張感の高い作業ばかりのおかげで、仕事の手際が良くなる
・病棟のようにひとりきりで仕事をするような場面がなく、常に執刀医・麻酔医・先輩看護師らと一緒にいる。それらの人のチェックが入るので、新人向き
・病棟勤務に移っても、手術前・手術後の患者さんへの理解が深まる
などが理由になります。
マイナスに考える人
やはりどうしても…
・あまりに仕事内容が特殊なので、ほかの診療科へ移った時に経験が生かせない・評価されない
という声が多いようです。